新築建替えと再生住宅、性能・コスト比較 – 1級建築士 本告のコラム
<「建て替えとリノベーション、どちらが得か?」という問いに応えるために>
「新築とリノベーション、どちらがお得ですか?」これは、私たちが日々いただくご相談の中でも、特に多い質問のひとつです。確かに、建物の性能やコスト、将来性などを冷静に見極めるには、両者の違いを正しく理解する必要があります。新築建替えと再生住宅(リノベーション)それぞれの構造・性能・コストの特徴を整理しながら、検討に必要な基礎知識をご紹介します。

<まず知っておきたい「坪単価」という考え方>
住宅の性能やコストを比較するうえで、避けて通れないのが「坪単価」という指標です。これは、建物本体の価格を延床面積(坪数)で割ったもので、「1坪(約3.31㎡)あたり、いくらで建てられるか」を表します。
ただし、この「坪単価」はあくまで目安であり、ハウスメーカーや工務店によって算出方法や含まれる費用が異なります。そのため、内容をよく確認することが大切です。
一般的に坪単価に含まれるのは、「家そのものを建てるための工事費用」が中心であり、以下のような費用は別途かかるケースが多く見られます。
- 外構(庭や駐車場など)
- 地盤改良や解体工事
- エアコン・照明・カーテンなどの設備
- 設計費や登記費、住宅ローン手数料、保険料などの諸費用
これらの費用を含めると、最終的な「家づくりの総額」は、坪単価の20〜30%ほど上乗せされるのが一般的です。したがって、坪単価はあくまで「比較のための目安」として捉えることが重要です。
それを踏まえたうえで、新築と、リノベーション、それぞれの特徴を見ていきましょう。
<コストと坪単価の見え方>
新築メーカーのコストと坪単価
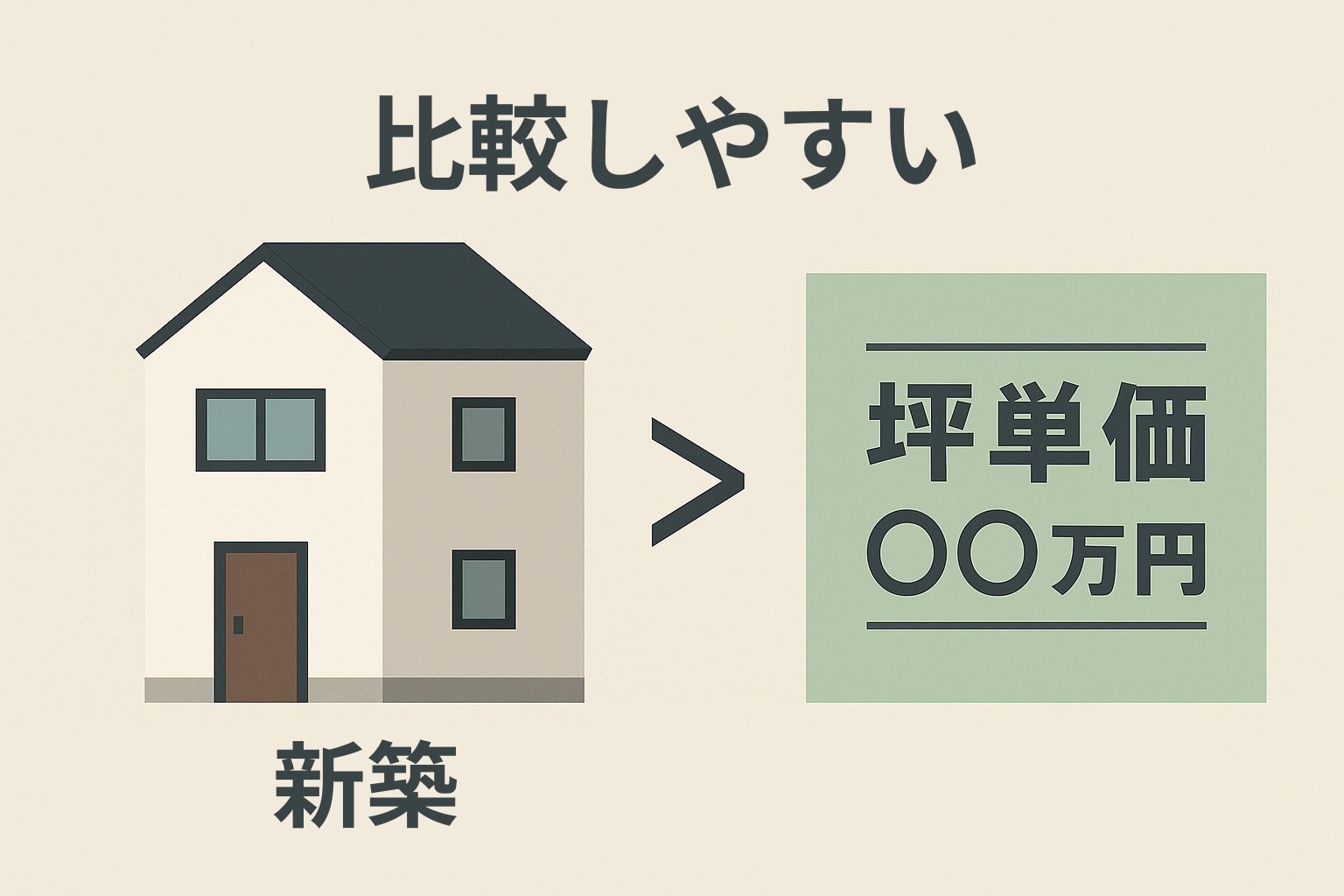
新築住宅は、更地からスタートするという特性上、仕様や費用の比較がしやすく、「坪単価○○万円」という表示がよく使われます。
多くの新築メーカーは、広告上の坪単価をできるだけ安く見せるため、シンプルな仕様(断熱性能や建材、設備など)を基準とするのが一般的です。
しかし、実際の家づくりでは、施主の要望に応じて断熱グレードや仕上げ材、設備、間取りなどが加わり、最終的な坪単価は当初より大きく上がる傾向にあります。
リノベーションのコストと坪単価
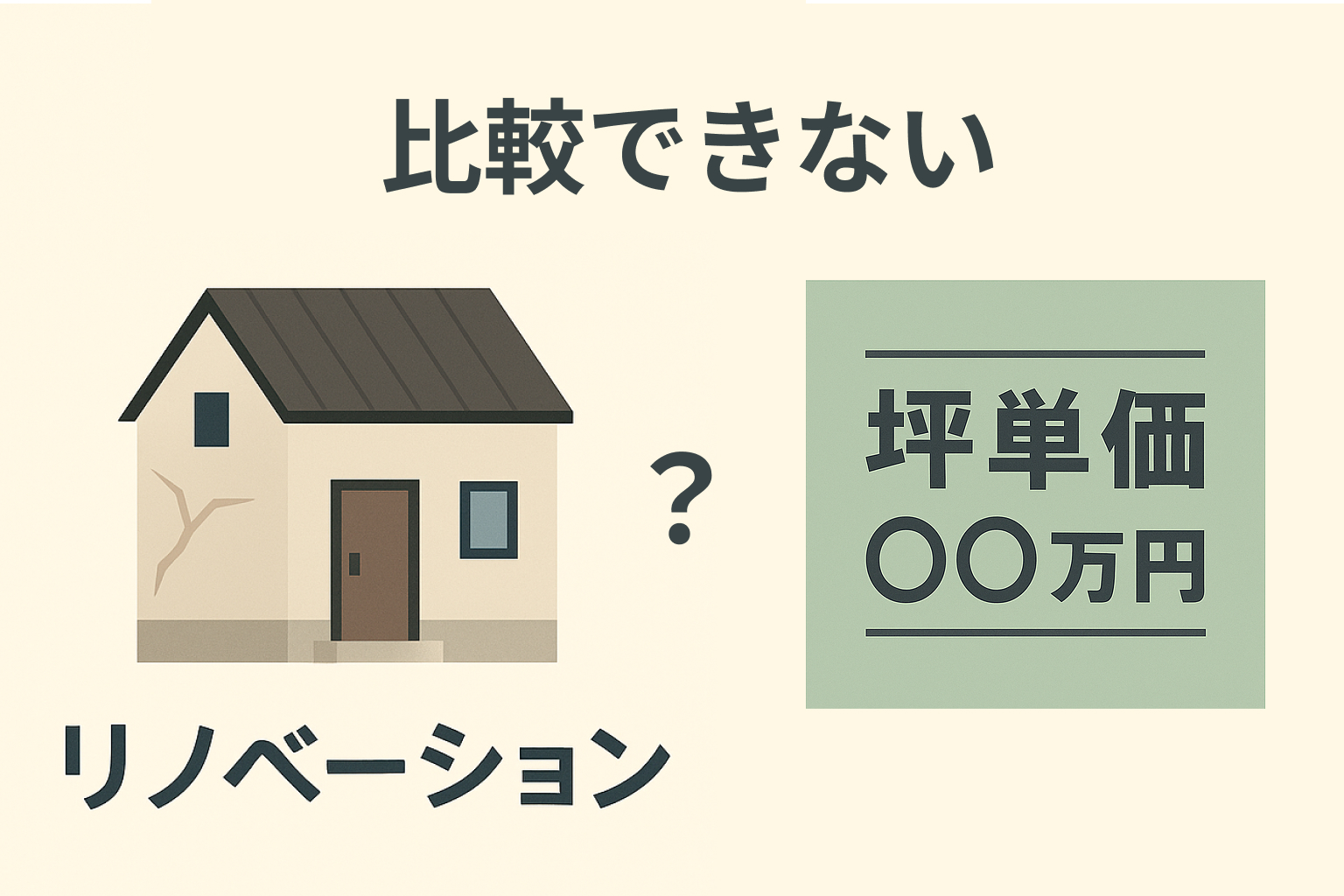
一方リノベーションの場合は、既存建物の状態が千差万別であることから、坪単価による単純な比較は成立しません。既存建物の調査結果によって必要な工事内容が左右されるため、コストや坪単価が大きく変動するという点が、リノベーションならではの特徴です。
ただし、条件によってはコストを抑えやすい側面もあります。
たとえば、既存建物に大きな傾きがなければ、新築と違って地盤改良が不要、また、建て替えと違って建物すべてを解体・処分する必要もありません。部分的な解体で済み、構造躯体や基礎をそのまま活かすことができれば、解体・新設にかかる費用を抑えることが可能です。
さらに、リノベーションでは「工事をしない部分」をあえて残すという判断もできます。今は使わない部屋や将来に備えた空間、状態が良好で手を加える必要のない部分などを見極めながら、全体の工事費を柔軟に調整できます。
以上を踏まえると、「同じ形状・同じ要望」であれば、新築よりリノベーションの方が安くなるのが自然です。
<ローコスト住宅メーカーが企画する高性能住宅とは?>

近年の新築住宅におけるニーズは、「安心・安全・高性能でありながら、できるだけコストを抑えたい」というものが主流になりつつあります。こうした流れは国の住宅政策とも連動しており、「高性能・省エネ・長寿命化」への優遇が年々強化されています。
住宅業界全体がその恩恵を受けるなか、特にローコスト住宅を主軸とするメーカーは、高性能化と価格競争の両立という課題に直面しています。その結果として、「耐震等級3」や「断熱等級7」といった最高等級をうたいながらも、「坪単価70万円台〜」という非常に魅力的な価格帯の住宅が生まれています。
このような“高スペック・低価格”を両立させるために、設計には徹底した合理化が図られています。
合理化された箱型高性能住宅の工夫
- 総2階建てで真四角に近い箱型形状
- 屋根・外壁・基礎の面積を抑えやすい構造
- 窓は小さく、数も最小限にする
設計意図と特徴
このような箱型高性能住宅では、できるだけ立方体に近い総2階建てを基本形とすることで、外皮面積を最小化し、屋根・外壁・基礎といったコストがかかる部分を抑制しています。さらに、窓を減らしたり小さくすることで断熱性や耐震性を高めながら、サッシや開口部のコストも削減しています。
こうした徹底した合理化により、コストダウンしつつ、「耐震等級3」「断熱等級7」といった高い性能を向上させることを狙います。
ただしその反面、以下のような注意点もあります。
- 階段の上り下りが避けられない(垂直動線が必須)
- 平屋や1階を広くとる設計は、コストアップにつながりやすい
- 個性や意匠性は限定され、間取りが画一的になりがち
このように「高性能をできるだけ安価に実現する」ことに特化した箱型新築は、非常に合理的で優れた選択肢の一つですが、特性を理解したうえで選ぶことが重要です。
<和づくりや古民家など、伝統的な日本家屋の特徴、そのリノベーション>
株式会社リノベ古民家モデルVIEW MORE>>
伝統的な日本家屋。いわゆる「和づくり住宅」や「古民家」には、現代の箱型新築とは対照的な設計思想が伺えます。これらの住まいは、平屋もしくは1階を重視した二階建てが多く、南側に天井の高い続き間を設けることで、開放的な大空間と自然との調和を実現しています。
築48年の平屋・セカンドハウスへリノベーションVIEW MORE>>
構造面では、太い柱や梁を用い、揺れても倒れにくい「変形を許容する設計」が特徴です。地域の風土に適した地元の材木を使い、大工の技術と美意識を凝らした「化粧造り」によって、構造そのものが美しさを担っています。
和づくり住宅・古民家における「間取り」の良いところ
- 南側に天井の高い続き間があり、大空間としての伸びやかさを感じられる
- 日当たりや風通しなど、地域特性に沿った自然との調和設計
- 庭に向かって開放的につくられており、内と外が一体となる暮らし
和づくり住宅・古民家における「間取り」の改善が必要なところ
- 台所が北側にあり、暗く寒くなりやすい
- 中廊下や広縁などの動線に面積が割かれ、空間効率が悪い
- 続き間や和室中心で個室が少なく、現代のライフスタイルに合わない場合もある
→これらは間取り変更により柔軟に対応可能です
また、断熱性・気密性に課題があることも少なくありません。無断熱や隙間風、そして外皮面積が大きいことによる断熱工事の負担増といった点は、断熱補強の際のコスト要因になります。さらに、耐震性に関しても、偏心(建物の重心と剛心のズレ)が生じやすく、南側の開口部が大きいことが構造バランスの課題となるため、必要に応じた補強が求められます。
 |
 |
 |
 |
とはいえ、こうした住まいは、リノベーションの素材として非常に高いポテンシャルがあります。良好な構造を活かしつつ、性能と間取りを現代的に再構築することで、新築にはない深みと個性を持った住まいをつくることができます。
施工事例
 |
 |
 |
 |
施工事例VIEW MORE>>
なお、同じような意匠を新築で一から再現しようとすると、無垢材や塗り壁、瓦屋根、特注建具などの要素が積み重なり、坪単価100万円以上になることも少なくありません。中には、ブランド材を使用し、数年をかけて建てられる総工費1億円超の新築事例も存在します。
<過去、価値のある建物を作ったから残す意味がある>
リノベーションは、既存の建物に現代の暮らしに求められるデザインや間取りを加えるアプローチです。必要に応じて断熱性や耐震性を補強しながら、住まいの価値を次世代へとつないでいく、実践的な住まいづくりといえます。
築年数が経過している住宅では、性能面に課題があることが多く、たとえば断熱等級5(ZEH水準相当)、耐震等級1(現行基準)を目指す場合には、相応の補強・改修が必要です。そのため、リノベーション費用は坪あたり50〜100万円程度が目安となり、条件によっては箱型新築以上のコストがかかるケースもあります。
当然、「リノベーションだからこそ、新築よりもコストを抑えられる」という本来の価値が損なわれないよう、適切なコストコントロールが重要だと私たちは考えています。ただし、その比較対象が「箱型新築だけ(=坪単価70万円程度)」になってしまうのは残念なことです。
私たちが重視しているのは、その住まいに宿る文化や空間の継承です。構造材の味わい、丁寧に組まれた架構、築古の家にしか出せない佇まいに、伝統と現代の技術で快適性と安全性を加える。そうした施しによって、新築とは異なる年代物(ヴィンテージ)としての魅力が生まれます。
さらに「物(建物や敷地、所有物件)」だけでなく、「人(家族構成や権利関係)」や「事(結婚や出産、相続やローンなど)」にも目を向け、紐解きながらデザインに落とし込む。そうして初めて、お施主様の暮らしに本当に寄り添った“たったひとつの住まい”をかたちにできると信じています。
<新築とリノベーション、どちらがお得か>
移住暮らしを叶えた夫婦の古民家風平屋VIEW MORE>>
もちろん、形状や仕様が同じであれば、リノベーションの方が安くなります。既存の構造体や基礎を活かせるため、工事の範囲が絞られ、材料費や解体費も抑えられるからです。
ただし実際のご相談では、比較の前提が揃っていないケースがほとんどです。
たとえば、
- 「和づくりの家を手放して、高性能な箱型新築へ建て替える」
- 「和の魅力を残しつつ、断熱・耐震性能を高めるリノベーションをする」
こうした比較は、そもそも形状も性能も目指す方向も異なります。このような場合、「どちらが得か」を単純に語ることはできません。
和づくりの新築という選択肢もありますが、コストは一気に跳ね上がります。
<家づくりは「価値観」と「優先順位」で決まる>
耐震性・断熱性向上で受け継いだ住まいVIEW MORE>>
家づくりにおいて最も重要なのは、「その家に何を優先したいのか」を明確にすることです。
もし、耐震性・断熱性といった性能を最重視し、限られた予算で効率よく建てたいなら、箱型の高性能新築が最適です。合理性とコストのバランスに優れています。
和づくりの良さも活かしつつ、耐震性や断熱性を一定水準まで引き上げたいという場合は、性能・コストとの折り合いを見極めたリノベーションが最も現実的な手段です。必要な部分だけを改修し、既存の構造や素材を活かすことで、コストコントロールが図れるのがリノベーションの強みです。
ご予算、立地、家族構成、そして何より「どんな暮らしを実現したいのか」。そのバランスによって、最適な選択肢は人それぞれ違ってくるものです。
既存の家があるというのは、とても恵まれていることだと思います。長く住まわれてきた建物には、図面には表れない価値があります。だからこそ私たちは、「本当にリノベーションがお客様にとって最良の選択か?」という出発点から、ご一緒に考えていけたらと願っています。
住まいは“比べて選ぶ”ものではなく、“納得して決める”もの。まずは「どんな暮らしを叶えたいのか」を整理するところから、ご一緒できたら幸いです。







